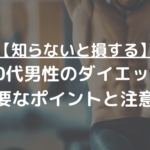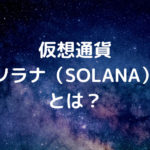近年、銀行預金の低金利や物価上昇の影響もあり、資産運用に興味を持つ方が増えてきました。
2024年から始まった新NISAも、資産運用する方にぜひ活用してほしい非課税制度です。
旧NISA制度で不十分だった点や、使いにくかった部分がパワーアップしたことで、より多くの方が利用しやすくなりました。
しかし、実際に新NISAを始めようとすると、「どこで証券口座を開設したらいいの?」と、さっそく壁にぶつかってしまう方も少なくありません。
そこで今回は、新NISAにさまざまな疑問を持つ方に向けて、口座開設時のポイントや金融機関ごとの違いについて解説します。
これから新NISAを始める方は、ぜひご参考にしてください。
目次
2024年から始まった「新NISA」とは
NISAとは少額投資非課税制度のことです。
本来、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISAを利用すると非課税になります。
少額かつ長期的に運用する方への税制優遇制度として2014年に始まりましたが、制度の大幅な拡充をきっかけに、2023年までの制度は旧NISA、現在の制度は新NISAと区別されています。
新NISAが新設するにあたって、旧NISAでは使いにくかった点が改善され、非課税の恩恵も大きくなりました。いくつかある新NISAの変更点のうち、重要なポイントは次のとおりです。
- NISA制度の恒久化
- つみたて投資枠と成長投資枠のふたつを併用可能
- 年間の非課税投資上限額が360万円
- 生涯の非課税保有額が大幅に増加
- 非課税で運用できる期間は無期限
新NISAが始まったことで、これまで投資をしてこなかった方も少額から投資経験を積みやすくなりました。
また、旧NISAの非課税枠では不十分だった方も、ふたつの枠を使って積極的な運用がしやすくなっています。
投資額や投資商品に関わらず、非課税の恩恵を受けながら自分にあった投資ができる点が大きな特徴です。
証券口座は、銀行と証券会社のどちらでも開設できます。
ただし、一人一口座しか持てず、変更するにも時間や手間がかかるため、基本的には同じ証券会社で運用を続けることになるでしょう。
証券会社の特徴をしっかりと抑え、納得したうえで開設することが大切です。
旧NISAとの違いは、こちらの記事でも詳しく解説しています。
【一覧表でまるわかり比較】新NISA口座を選ぶポイント
「銀行や証券会社はどこも同じように見えるけれど、どこで口座開設したらいいの?」と迷う方もいるかもしれません。
しかし、実際は金融機関ごとに新NISAの取り扱い銘柄やサービス内容は大きく異なっています。
たくさんの選択肢から自分に合ったものを見つけるために、さまざまな視点から金融機関を見比べてみましょう。
取扱商品数、銘柄数で比較
はじめに、新NISAの取扱商品数と銘柄数で比較してみます。
| NISA投資枠名称 | つみたて投資枠 |
成長投資枠 |
||
| 銀行・証券会社 | 投資信託対象商品数 | 投資信託対象商品数 | 日本株式取扱銘柄数 | 米国株式取扱銘柄数 |
| 三菱UFJ銀行 | 24銘柄 | 347銘柄 | × | × |
| みずほ銀行 | 14銘柄 | 114銘柄 | × | × |
| 三井住友銀行 | 4銘柄 | 88銘柄 | × | × |
| ゆうちょ銀行 | 15銘柄 | 56銘柄 | × | × |
| 楽天証券 | 220銘柄 | 1,115銘柄 | 4,402銘柄 | 4,730銘柄 |
| マネックス証券 | 217銘柄 | 1,101銘柄 | ※記載なし | 4,608銘柄 |
| 松井証券 | 222銘柄 | 1,062銘柄 | ※記載なし | 3,600銘柄 |
| auカブコム証券 | 217銘柄 | (877銘柄) | ※記載なし | 1,743銘柄 |
| 野村證券 | 19銘柄 | 408銘柄 | 4,805銘柄 | × |
取扱銘柄数は金融機関ごとに異なりますが、前半の銀行と後半の証券会社では、はっきりと差が出ていることが分かります。
銀行は銘柄数が少なく、成長投資枠に日本株や米国株といった株式投資は利用できません。
証券会社では、取り扱う銘柄数だけでなく、成長投資枠に日本株や米国株が多数含まれているのが特徴となっています。
取扱商品数や銘柄数で証券口座を決める場合、少なくて問題なければ銀行、多いほうがよければ証券会社と考えられるでしょう。
取引手数料で比較
長期的に投資を続けるなら、手数料というコストをいかに削減するのかも大事な比較ポイントになります。
なるべく取引手数料がかからない金融機関を選ぶのが望ましいです。
| NISA投資枠名称 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | ||
| 銀行・証券会社 | 投資信託 | 投資信託 | 日本株式 | 米国株式 |
| 三菱UFJ銀行 | 無料 | 一部有料 | × | × |
| みずほ銀行 | 無料 | 一部有料 | × | × |
| 三井住友銀行 | 無料 | 一部有料 | × | × |
| ゆうちょ銀行 | 無料 | 一部有料 | × | × |
| 楽天証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| マネックス証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 松井証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| auカブコム証券 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 野村證券 | 無料 | 一部有料 | 有料 | × |
つみたて投資枠はすべての金融機関が手数料を無料としている一方、成長投資枠に関しては銀行と証券会社で違う傾向が現れています。
銀行では、成長投資枠で選ぶ銘柄は一部有料です。
一見、手数料がかかるのはデメリットに感じられますが、つみたて投資枠のみを利用する場合は気にする必要はありません。
反対に、つみたて投資枠も利用したい場合には、証券会社が適しています。
投資金額や投資スタイルに合う金融機関を選ぶことがポイントです。
つみたて投資枠の条件で選ぶ
つみたて投資枠を利用するときの使い勝手のよさを重視している方は、最低積立額や積立のタイミングも要チェックです。
| NISA投資枠名称 |
つみたて投資枠 |
||
| 銀行・証券会社 | 最低積立額 | 積立のタイミング(月あたりの回数) | 積立の日付 |
| 三菱UFJ銀行 | 1,000円 | 毎月 | 自由に設定できる |
| みずほ銀行 | 1,000円 | 毎月 | 自由に設定できる |
| 三井住友銀行 | 10,000円 | 毎月 | 自由に設定できる |
| ゆうちょ銀行 | 1,000円 | 毎月 | 自由に指定できる |
| 楽天証券 | 100円 | 毎日・毎月 | 自由に設定できる |
| マネックス証券 | 100円 | 毎日・毎月 | 自由に設定できる |
| 松井証券 | 100円 | 毎日・毎月 | 自由に設定できる |
| auカブコム証券 | 100円 | 毎月 | 自由に設定できる |
| 野村證券 | 1,000円 | 毎月 | 毎月16日/27日
※引き落とし方法によって異なる |
表で比較すると、最低積立額は比較的証券会社のほうに低い傾向が見られます。
100円という少額から始められるので、家計への影響を最小限に抑えながら投資経験を積むことができるでしょう。
楽天証券、マネックス証券、松井証券は毎日積立もできます。
仮に100円を毎日積立に設定した場合、月の投資額は3,000円です。
少しでも投資タイミングを分散させたい方は、毎日積立のサービスがある証券会社が適しています。
新NISA口座を銀行で開設するメリット
金融機関ごとに新NISAのサービスを比較してみると、銀行と証券会社で大まかに分類できます。
実際に、銀行で新NISA口座を開設した場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
メリットとしては取り扱う銘柄が多すぎないことが挙げられます。
悩みやすい方にとってメリットとなり、投資経験が浅いうちは、多くの銘柄から自分に合う商品を見つけるのは大変な作業になるでしょう。
選ぶのが面倒になり、投資自体を辞めてしまっては本末転倒です。
始めから十数銘柄に絞られていれば、選ぶハードルは大きく下がります。
「投資はしたいけど、面倒な手間は掛けたくない」という方は、選択の幅を減らすのも方法のひとつです。
ただ、証券会社で新NISA口座を開設することと比較すると、銘柄数が絞られるほかにメリットは特にありません。
また、絞られることはデメリットにもなり、銀行で取り扱いの無い銘柄に投資しようとすると、煩雑な手続きをして口座を変更しなければなりません。
初心者のうち・あまり時間を割かずにNISAを利用したいという人以外は銀行での口座開設は控えた方が良いでしょう。
新NISA口座を銀行で開設するデメリット
それでは次に、新NISA口座を銀行で開設するデメリットについて、解説していきます。
成長投資枠で株式投資が利用できない
銀行を選ぶデメリットのひとつは、成長投資枠で株式投資ができないことです。
銀行での運用は、成長投資枠で一部の投資信託が選べるものの、株式は利用できないパターンが多く見られます。
成長投資枠でも投資信託を選ぶ方は問題ありませんが、長期的な運用の最中で「やっぱり株式投資もしたい」となることもあり得るでしょう。
取り扱う金融商品が始めから限られていると、投資金額や運用スタイルが変わったときに、調整しにくいことが予想されます。
取引手数料が基本有料
一部の商品で取扱手数料がかかるのも、人によってはデメリットと感じてしまうポイントです。
仮に運用で利益が出ていても、手数料分が差し引かれてしまうと結果的に運用効率は下がってしまいます。
手数料は数十円〜数百円とそう大きな金額ではありません。
しかし、一回ごとの手数料は微々たるものでも、数十年と繰り返していけばいずれ大きな金額となります。
新NISAが長期で運用する方を想定して作られた制度であると考えると、手数料はできるだけかからないほうがよいでしょう。
銀行を選ぶ場合は、取引手数料による影響を考慮したうえで利用することをおすすめします。
新NISA口座を証券会社で開設するメリット
続いて、新NISA口座を証券会社で開設するメリットとデメリットについて、まずはメリットからお伝えしていきます。
豊富な対象商品・銘柄から選べる
証券会社で開設するメリットのひとつ目は、対象商品や銘柄の幅広さです。
広すぎる選択肢が悩む要因となってしまう方もいますが、自分で投資判断を下せる方の場合は選択肢は多いほうがよいでしょう。
商品の特徴を把握し、自分の投資スタイルが定まっていれば、自然と銘柄はある程度絞れます。
自分の判断で運用したい方は、豊富な対象商品から選べる証券会社での運用がおすすめです。
取引手数料がほとんど無料
ふたつ目のメリットは、ほとんどの証券会社で新NISAの取引手数料が無料であることです。
長期投資で少しでも運用効率を上げるためには、細かな出費をいかに少なくするかがカギとなります。
購入する頻度が高く、長期で運用する方ほど大きなメリットとなるでしょう。
ただし、店舗型の証券会社は、取引手数料がかかる場合もあります。
証券口座を開設する前に、手数料までしっかりと確認しておきましょう。
メリット3:つみたて投資枠での積立方法が比較的自由
3つ目のメリットは、つみたて投資枠での積立が比較的自由に設定できることです。
証券会社によっては100円という少額から利用でき、積み立てるタイミングも自分で決められます。
最低投資金額が10,000円の金融機関の場合、ひと月の予算が10,000円ならひとつのファンドにしか投資できません。
しかし、最低投資額が100円の金融機関であれば、10,000円の投資金額で100ヶ所まで分散可能です。
少額投資なら、時間の分散だけでなく投資先の分散もしやすくなるでしょう。
投資額に関わらず、自由に決められることが大きなメリットです。
新NISA口座を証券会社で開設するデメリット
続いてデメリットですが、証券会社の自由度の高さは、人によってデメリットになり得る可能性があります。
投資する金融商品や投資金額、積立日の設定など、銀行と比べて自分で判断する機会が多いためです。
「投資にあまり時間を割きたくない」という方には、証券会社での運用は面倒に感じてしまうかもしれません。
選択肢の多い新NISAで迷いなく利用するためには、「どんな投資がしたいか」「将来いくらの運用益が欲しいか」など、あらかじめ自分の投資方針を定めておくことが大切です。
ライフイベントによって投資方針が変化した場合は、その都度投資計画を組み直しましょう。
新NISAで投資したいおすすめ投資信託
ここからは、新NISAでつみたて投資枠の対象商品である、おすすめの投資信託を3つご紹介します。
「投資先がなかなか決まらない…」という方は、ぜひご参考にしてください。
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)は、国内と海外先進国、新興国すべての株式を投資対象とするインデックスファンドです。
オール・カントリーという名前のとおり、この投資信託1本で世界中の株式に分散投資できます。世界中の経済状況の変化に合わせて、自動的に銘柄を組み替えてくれる使い勝手のよさも人気の理由のひとつです。
また、全世界をカバーしつつも、比較的低い運用コストで運用しています。
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)を含む「eMAXIS Slimシリーズ」は、運用会社である三菱UFJアセットマネジメントが「業界最低水準の運用コストを目指す」というコンセプトを掲げており、実際に信託報酬の引き下げを積極的に行ってきました。
同シリーズの「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」や「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」も大変人気があります。
楽天・全米株式インデックス・ファンド
楽天・全米株式インデックス・ファンドは、米国市場の銘柄に広く分散する人気のインデックスファンドです。
マザーファンドを通じて米国の人気ファンド「VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)」に投資を行っているため、「楽天・VTI」の名前でも親しまれています。
VTIは世界最大級の運用会社バンガード社が運用しているETFです。
誰もが知っているような大型株から中・小型株までカバーする網羅性と、経費率が低いことでも評価されています。
この投資信託もVTIと同じ指標に連動するように運用しており、近年の純資産額は右肩上がりです。
楽天・全米株式インデックス・ファンドは、米国全体に投資できる投資信託をお探しの方に適しています。
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド
インデックス型の投資信託で日本株に投資したい方には、三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンドをおすすめします。
TOPIX(東証株価指数、配当込み)を指標としており、投資先は日本株が100%です。
組入銘柄の上位には、トヨタ自動車やソニーグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループなど、日本が誇る大企業が並んでいます。
国内の株式に投資している同分類のファンドの中では、コストも十分に抑えられている商品です。
国内株に投資したい方や、ほかの金融商品との分散を図りたい方に向いています。
新NISAで口座開設したい証券会社3選
最後に、ここまでの比較結果を踏まえ、取扱銘柄数や使いやすさに優れた証券会社を3つ紹介します。
楽天証券
楽天証券は、国内最大手のネット証券の一角を占める証券会社です。
新NISA対象の取り扱い銘柄が多く、多くの方から選ばれる人気の投資信託はもちろん、株式やETFなどさまざまな金融商品を組み合わせられます。
操作画面が分かりやすいことでも知られており、初心者でも迷わずに利用できるでしょう。
また、ポイントを使って現金と同じように運用できる「ポイント投資」や、楽天銀行と連携し、証券口座に自動入金できる「マネーブリッジ」など、楽天証券は利用者が便利に使えるサービスが豊富です。
楽天グループのサービスを使っている方なら、楽天証券を利用すると、さらにポイントを貯めやすくなるでしょう。
「幅広い選択肢が欲しい方」や「楽天ユーザー」におすすめの証券会社です。
auカブコム証券
auカブコム証券は、2019年に誕生したネット証券会社です。
まだ開始して間もないように感じますが、過去に「日本オンライン証券」「カブドットコム証券」などを運営しており、実績は十分にあるといえます。
通信業の大手企業KDDIと三菱UFJフィナンシャルグループが共同で運営しており、サービスの手厚さも評判となってユーザー数を伸ばしています。
投資信託を保有しているだけでPontaポイントが貯まり、ポイント投資ができるのも大きな特徴です。
100円から利用できるので、現金を使わずにポイントでお試ししてみるのもよいでしょう。
また、au PAY ゴールドカードの保有やカード決済、「auマネ活プラン」の加入などを組み合わせることで、ポイント還元率は最大3%(12ヶ月まで)まで上昇します。
付与されるポイントを有効活用し、お金を貯めるサイクルを生み出しやすい点が大きな魅力です。
松井証券
松井証券は創業100年以上の歴史を持ち、日本で初めてネット証券に参入した老舗の証券会社です。
YouTubeなどでも積極的に発信を行い、初心者にも投資が身近に感じられるような分かりやすい解説を行っています。
投資信託の残高に対し、年間最大1%のポイントがたまる「残高ポイントサービス」も評判です。
便利でお得なサービスを次々と打ち出しているのも、高い信頼を得ている理由のひとつでしょう。
新NISAにおいては、売買手数料の永年無料をいち早く発表したことで知られています。
投資信託の取り扱い数はネット証券会社には及びませんが、つみたて投資枠の対象商品数は他の会社をおさえNo.1となりました。
最低積立額も100円と低く、使い勝手も申し分ありません。
ただし、一日の取引金額が50万円を超えると取引手数料がかかってしまうことに注意です。
新NISAを利用する分には問題ありませんが、通常取引において大きい金額を運用するときは注意しましょう。
まとめ
銀行と証券会社では、新NISAの取り扱いやサービスが大きく異なります。
顧客獲得のために独自のサービスを提供している金融機関も多く、口座開設までの選択がより難しくなっているのが現状です。
新NISA口座は1人ひとつまでしか持てないため、後悔のない選択が必要になります。
事前に自分の投資スタイルや、投資枠の使い分けを考えておき、求めるサービスが備わっている金融機関で口座を開設しましょう。
実際に金融機関のホームページなどで銘柄検索などの操作を行ってみて、使いやすさも確かめてみてくださいね。